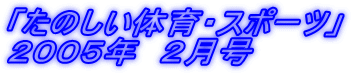



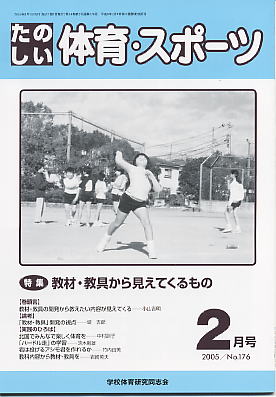 |
 【巻頭言】 教材・教具の開発から教えたい内容が見えてくる (小山吉明) 【論考】 「教材・教具」開発の視点(堤 吉郎) 【実践のひろば】 北国でみんなで楽しく体育を(中村訓子) 「ハードル走」の学習(茨木則雄) 君は投げるアシモ君を作れるか(竹内由美) 教科内容から教材・教具を(岩崎英夫) 【教材一工夫】 教具をこう工夫した (障害児体育分科会・同OB) 【2004年学校体育研究同志会第129回全国大会・冬大会報告】 同志会の基礎技術論を見直す(大貫耕一) |
 -編集者から一言- 体育の教材・教具は様々な教師により数多く生み出されています。また教材販売会社などのカタログにも様々な教具の類が載っています。これらは、逆上がり補助器や、閉脚跳び越し用に中央部分が凹形に削られた跳び箱のように、学習者の運動を補助し、よりよい動きをつくっていくために工夫・開発されたものがほとんどです。 しかし、マットの手形・足形や心電図・田植えラインなど同志会の生み出してきた教材・教具は運動を補助する教具とは異なり、「何を教えたいのか」「何をわからせたいのか」という教科内容研究から生み出されています。 たとえば田植えラインでは、子どもたちの走りの出来具合がひと目で映し出されます。それは、短距離走で教えたい中味「最高速度を持続する技術」を学ばせるために、トップスピードに達した時点で起こるリズムの乱れを子どもたちの目に見える形で提示するからです。教師の中にある「何を教えたいのか」「何をわからせたいのか」という教科内容についての研究が、教材・教具の開発につながっているのです。2月号では、教材・教具の視点から実践を見つめ、どのような教科内容に基づき、どのようなことを子どもたちに学ばせ、そしてできるようにさせようとしたのかを探ってみたいと考えました。お楽しみに。 (たのしい体育・スポーツ 編集委員 水谷 淳) -「同志会東京」 №348 より- |
 ■教材12ヶ月:自己肯定感を育む「みんどこ?」授業(伊藤真理) ■私の指導案:子どもを授業の主体者に2(下山寛美) ■私たちの授業研究:みんなに広げようフラッグフットボール (一瀬栄政) ■教育情報:義務教育費国庫負担制度をめぐる動き(渡辺孝之) ■図書紹介:(黒川哲也/三木幸子/吉末 功) ■情報ノート:(塩井輝男) ■読者の声:(佐藤正浩/藤野直子) ■東西南北:(久保雅一/岨 和正) ■編集後記/次号予告 |