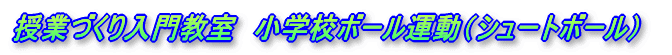

|
そのための授業をどうつくるのか? -発達の特徴からみた学習課題と教材づくり・授業づくり- |
大会基調をどう受け取り、分科会に反映させていくか
大人から子どもまで、だれでも手軽に楽しめて、しかも燃える中身がいっぱい詰まった教材なので、ぜひ体験して持ち帰っていただきたいと思います。また、使うボールやゴールの大きさや形状やゲーム人数などを含めたルール変更により、ゲーム内容が大きく変わり、教えたい中身も変わってくることを、実技の中で理解していただければ、授業づくりの上ですごく役に立つと思います。
何よりも参加されたみなさんの誰もが「ボール運動の楽しさ」と「教える楽しさ」を味わえるような講座にしたいと思っています。
分科会Ⅰを終えて(感想)
・初めてシュートボールをしました。今まで球技をしてきたけれど、いろんな所にシュートできるのが新鮮でした。いろんな絵を使えば、子どもたちも楽しんでシュートできそうだと思いました。
★1クラス25人のとき、1対1のゲームに参加できるのは8人で、残りの子はどうしているのでしょうか。(Kさん、滋賀)
・ゲームを初めてやってみて、とても楽しかったです。私は球技が苦手ですが、シュートボールはとても楽しめたので、子どもとやってみたいなと思いました。的の大きさを変えたり、人数を変えたりして工夫できるので、おもしろいなと思いました。
★2人ずつゲームをしていくときは、待っている子はどんな感じですか? 的を直したり、点数を入れたり、応援したりですか?(Kさん、滋賀)
〈コメント〉KさんとKさんの質問に対して
1対1のゲームのときに、たくさんの子どもがクラスにいても、的を直す役割の子、点が入ったことを知らせる役割の子、点数の磁石をはる役割の子、時間をはかる役割の子など、たくさんの役割をさせてあげると結構みんな関わることができますよ。
2人ずつゲームするときも同様です。明日はそういう役割もみなさんにやっていただいて、体験してもらいましょうね。(Kさん、Hさん、Mさん)
分科会の柱、大切にしたいこと
・どの子もシュートの楽しさを味わうためのボール運動の授業のつくり方をどうするのか。
・ボール運動の中で、「動きづくり」を中心においた時に、どのような教材がふさわしいのかを考える。
・目の前の子どもの実態に合わせ、その子たちに何を教えたいかという中身によって教材や授業をつくるということ。
分科会Ⅱ(感想)
・汗をたくさんかきながら、楽しくシュートボールができました。中学年だけでなく、ルールやチーム編成を変えれば、全学年で行えるとあり、さっそく2学期の授業で実践してみます。
360度どこからでもゴールが狙えるというのが良いと思います。ビデオで試合を撮るというのもいいですね。(Kさん、滋賀)
〈コメント〉
今日の実技でゴールの大きさやルール、ゲーム人数によってゲーム内容が大きく変わるということを実感していたのだったと思う。逆に言えば、子どもの実態や教える中身に合わせて、教具やコート、ルールづくりを子どもたちといっしょにつくり上げていくことが大切ですね。授業づくりのポイントがそこにあると思います。(Kさん、兵庫)