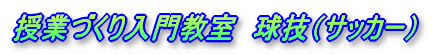

|
舩冨公二(大阪支部) |
大会基調をどう受け取り、分科会に反映させていくか
①球技(サッカー)の指導の系統における「叢書」批判からはじまり、指導の系統と児童生徒の認識やからだの発達と統一した学習システムとして、「サッカー指導における階層システム」を作り上げてきた。
②その階層システムに教科内容研究の成果を私なりに入れ、その実践にも取り組んだ。
③「じゅまじゃまサッカー」は「階層システム」の実践過程で生み出された。
分科会Ⅰを終えて(感想)
・サッカーは初めてやって、最初はとても戸惑いました。ボールが見えず、コートも見えなくて、いっぱいいっぱいでした。
しかし、回を重ねるにつれ、ドリブルらしいものができるようになり、チームの方々の協力で、なんとかシュートできた時は、とてもうれしかったです。
自分がどこにいればいいのか、自分で考えて動くということが、頭を(体も)使うことだと思いました。サッカーをはじめ多くのスポーツは、体はもちろん、主体的に考え積極的に動かなきゃと思いました。(Mさん、愛知)
・順を追って、一人一人が参加できるように進めていくこと、また、楽しんで参加できるようにすることが大切なんだと感じました。私は、サッカーをあまりやったことがなかったので、難しかったけれど、パスやドリブルを楽しみながら参加することができました。しかし、やはり自分があまりできないので、指導方法もわかっていないので、また明日しっかり学びたいです。
まだ自分ができないし、しっかりやった経験がないので、一つ一つ学んでいきたいと思います。上手な人もたくさんいるので、見ながら、そして参加しながら学んでいきたいです。(Yさん、愛知)
〈コメント〉
今回の参加者は、サッカーの経験者が多かったので、スイスイとボールを操作し、二段階ではパスを出していましたが、コンビネーションの学習は明日ですから、がんばりましょう。(Hさん、大阪)
分科会の柱、大切にしたいこと
・小学校低学年期、中学年期の児童の発達で著しいのは巧緻性の発達である。
・小学校低学年期から身体操作、ボール操作の学習が必要。
・小学校低学年期、中学年期の児童には、練習ではなく遊び感覚・ゲーム感覚で学ばせる方が身につく。
・「サッカー指導における階層システム」の第1、第2段階(低学年)の技術面の学習課題は、「ドリブルシュートとそれへの守り」であること。
・どの年齢においても技術的な傾斜はあるが、どの子も楽しく遊べて上達でき、小学校低学年期、中学年期の課題に対応した教材が「じゃまじゃまサッカー第1バージョン」である。
分科会Ⅱ(感想)
・ルールが徐々に難しくなってくると、動きも複雑で、わからなくなりました。子どもたちにやらせるときは、くり返し何度もやる必要があると思いました。でも、慣れてきて、自分たちで作戦を考えてできるようになれば、あまり上手くない子でも楽しめると思いました。
ルールが結構複雑なので、子どもたちに対して、どううまく説明するかが課題だと感じました。(Sさん)
〈コメント〉
『じゃまじゃま基礎技術バージョン』で、パスの出し方のタイミング、走り込む場所とコース・タイミングをみっちり学習することが大切です。『攻防の切りかえバージョン』は、その後の課題ですので。(Fさん、大阪)
分科会Ⅲ(感想)
・サッカーはサッカーでも、攻守別々にするというところが低学年、中学年の子どもたちにとって理解しやすいと感じました。ボールに恐怖感を持つことなくゲームを進めていくために、サッカーの楽しさを工夫して伝えられればな、と思いました。(Sさん)
〈コメント〉
1段階から基礎技術バージョンまでを実技しましたが、サッカー経験者の方などのアドバイスもあり、異質集団がうまく教え合いながら学んでいただけました。なお、自分の前に防御がいないときはドリブルで攻める積極性を持ちましょう。(Fさん、大阪)